✏️ はじめに
少し前まで、街を歩けばあちらこちらで見かけたタピオカドリンクのお店。キラキラしたお店の前には、長い行列ができていることも珍しくありませんでした。でも最近、気がつけば、以前ほどタピオカ屋さんを見かけなくなったような気がしませんか?
「そういえば、あの人気のお店、どこへ行っちゃったんだろう?」
今回のレポートでは、かつて日本中で大ブームを巻き起こしたタピオカドリンクのお店たちの物語をひも解きながら、お店を始めることや、お店がどのようにして儲けているのかといった、ちょっと難しいけれど面白いビジネスの秘密を、みんなにもわかりやすく解説していきます。
📝 タピオカドリンク、過去にはこんなに人気だった!
タピオカドリンクは、まさに「ブーム」を何度も経験してきた食べ物なんです!
第一次ブーム(1992年頃)
日本でタピオカドリンクが最初に注目されたのは、1990年代初めのこと。この頃は、「エスニックブーム」という時代で、その流れに乗って、白いタピオカが入ったココナッツミルクが人気を集めました。
第二次ブーム(2003年頃~2009年頃)
この頃には、「パールレディ」という日本で初めてのタピオカ専門店が登場したり、台湾の「Quickly」や「EasyWay」といったお店が日本に進出。白いタピオカから黒いタピオカを使った「タピオカミルクティー」が人気になりました。
第三次ブーム(2013年頃~2019年頃)
「平成最後の食ブーム」とも言われるほど、ものすごい人気でした。台湾の有名店「春水堂(チュンスイタン)」の日本進出がきっかけとなり、その後「ゴンチャ」や「THE ALLEY」といったおしゃれなタピオカドリンクのお店が次々とオープン。
💡この頃のブームを語る上で欠かせないのが、SNSの存在です。「インスタ映え」という言葉が流行し、見た目が可愛くておしゃれなタピオカドリンクの写真をSNSにアップすることが、一つの楽しみになりました。
| ブーム | 時期 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 第一次 | 1992年頃 | タピオカココナッツミルク |
| 第二次 | 2003-2009年頃 | タピオカミルクティー登場 |
| 第三次 | 2013-2019年頃 | 「タピる」という言葉誕生 |
タピオカ市場規模の推移
🔍 ブームの秘密:なぜみんなタピオカに夢中になったの?
なぜ第三次タピオカブームは特に大きかった?
SNSの普及によって、若い世代が新しい情報を共有しやすくなったことが挙げられます。友達がSNSにアップしたおしゃれなタピオカドリンクの写真を見て、「美味しそう!」「私も行ってみたい!」と感じる人が多かったのでしょう。
✨この時期に登場したタピオカドリンクのお店は、単にタピオカが入った甘い飲み物を提供するだけでなく、お茶そのものの品質にこだわった「ティースタンド」という新しいスタイルを打ち出しました。
「ゴンチャ」のように、甘さや氷の量、トッピングなどを自分好みにカスタマイズできるお店も登場し、お客さんにとって特別な体験ができるようになりました。
そして、何と言っても、あのモチモチとしたタピオカの独特な食感が、多くの人を夢中にさせた大きな理由です。
📊 あれからどうした? 今、タピオカ屋さんはどこに?
あれほど人気だったタピオカドリンクのお店ですが、2019年頃をピークに、その勢いは徐々に落ち着きを見せ始めました。どんなブームにも終わりが来るように、タピオカ人気も少しずつ変化していったのです。
🔄ブームが落ち着いた理由
- たくさんのお店がオープンして珍しさが薄れた
- 2020年以降の新型コロナウイルスの影響
- 人々の興味や関心の対象の移り変わり
現在、街で見かけるタピオカ屋さんの数は、ブームの頃と比べるとかなり減りました。特に、個人で経営していたような小さなお店の多くは閉店してしまいました。
かつて「タピオカの聖地」と呼ばれた原宿では、2019年にあった26店舗のうち、18店舗が閉店したという調査結果も!
その一方で、「ゴンチャ」のような大手チェーン店は、お茶の品質にこだわり、カフェとしての居心地の良さも提供することで、人気を維持し、店舗数を増やしているところもあります。現在、日本では160店舗以上を展開しているそうです。
📚 本を読んでみよう!
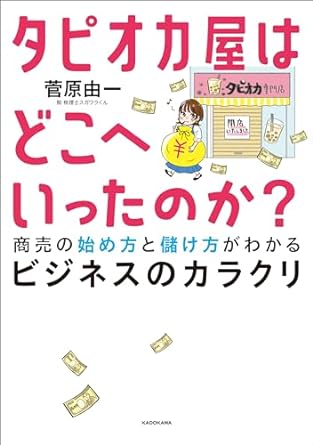
タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ
この本は、かつてブームになったタピオカ屋さんを例に、お店を始めるにはどんなことを考えなければいけないのか、そして、どうすればお店が儲かるようになるのかといった、ビジネスの基本的なしくみを、小学生にもわかりやすく解説してくれる本です。
Amazonで見る
💡 なるほど! タピオカ屋さんで「儲ける」ってどういうこと?
では、タピオカ屋さんが「儲ける」というのは、どういうことなのでしょうか? この本では、お店が儲かるための基本的な考え方も、小学生にも理解できるように解説されています。
💰売上:お店が商品を売って得たお金のこと
例:タピオカドリンクが1杯500円で、1日に100杯売れたとしたら、その日の売上は500円 × 100杯 = 50,000円
💸費用:お店を運営するためにかかるお金のこと
・タピオカドリンクの材料(お茶、牛乳、タピオカなど)
・カップやストローなどの消耗品
・お店で働くスタッフの人件費
・お店の家賃
・カップやストローなどの消耗品
・お店で働くスタッフの人件費
・お店の家賃
✅利益:売上から費用を差し引いた残りのお金
例:タピオカ屋さんの1日の売上が50,000円で、かかった費用が30,000円だった場合、利益は50,000円 - 30,000円 = 20,000円
お店は、利益を増やすために、材料を安く仕入れる方法を探したり、たくさん売れるように工夫したりするんだよ!
🧠 タピオカ屋さんの裏側をのぞいてみよう:ビジネスのしくみ
ビジネスの視点から見たタピオカブーム
タピオカ屋さんの盛衰の物語は、ビジネスの様々な側面に当てはめて考えることができます。
🔄競争と差別化
たくさんのお店ができたということは、競争が激しくなったということ。そんな中で、人気を保つためには、他のお店よりも美味しいドリンクを提供したり、魅力的なサービスを考えたりする必要がありました。
👥顧客ニーズの理解
成功しているお店は、お客さんが何を求めているのか、つまり顧客のニーズを理解することができていたと言えるでしょう。「ゴンチャ」がコーヒーの提供をほとんどの店舗でやめて、ティー専門店としてのイメージを強くしたのは、コーヒーが苦手な人にもっとお茶を楽しんでもらいたいという考えがあったからです。
📝 まとめ:タピオカ屋さんからお金と仕事の面白さを発見!
今回のレポートでは、かつて大人気だったタピオカ屋さんの歴史を振り返りながら、そのブームの秘密や、お店が減ってしまった理由を探ってきました。そして、タピオカ屋さんを例に、お店を始めることや、儲けることの基本的なしくみを解説した本「タピオカ屋はどこへいったのか?」を紹介しました。
この本を読むと、タピオカ屋さんだけでなく、身の回りの様々なお店が、どんなことを考えて、どのようにして私たちに商品やサービスを提供しているのかが、きっとわかるはずです。
お金の流れや仕事のしくみについて学ぶことは、少し難しそうに感じるかもしれませんが、この本は、みんながよく知っているタピオカ屋さんを入り口に、楽しくビジネスの世界をのぞかせてくれます。小学生のみんなも、そしてその親御さんも、ぜひこの本を読んでみてください!